第1章:PER(株価収益率)とは?基本概念
PER(Price Earnings Ratio、株価収益率)とは、株価が1株あたりの利益(EPS)に対してどの程度割高または割安かを示す指標です。 投資判断の基本となる評価指標の一つであり、株式投資初心者からプロ投資家まで幅広く活用されています。
計算式は単純で以下の通りです。
PER = 株価 ÷ 1株当たり純利益(EPS)
例えば、株価1,000円、EPS100円の銘柄であれば、PERは10倍となります。
第2章:PERの計算方法と種類
PERには複数の計算方法があり、用途によって使い分けます。
1. 過去実績ベースPER(Trailing PER)
過去1年間のEPSを用いて計算する方法です。実績に基づくため安定性があり、企業の過去の利益との比較に有効です。
2. 予想PER(Forward PER)
企業が発表する今後1年間の予想EPSを用いて計算します。将来の成長性を織り込んだ指標で、投資判断の参考になります。
| PERタイプ | 計算対象EPS | 用途 |
|---|---|---|
| 過去実績PER | 過去1年のEPS | 実績評価、過去比較 |
| 予想PER | 今期予想EPS | 成長見込み評価、将来予測 |
第3章:PERの見方と活用法
PERの数値は、一般的に「高い=割高」「低い=割安」と解釈されますが、業種や成長率によって適正PERは異なります。
- 成長株:将来の利益拡大が見込まれる場合、高PERでも投資価値あり
- 成熟株:利益成長が安定している場合、低〜中PERが割安判断の目安
- 業種比較:同じ業種内で比較することで相対的割安・割高を判断
📊 PERのイメージ図
株価 1,000円 / EPS 100円 → PER 10倍 → 割安の目安
第4章:PERを使った投資実践例
例1:業種平均との比較
業種平均PERが15倍の中、銘柄AのPERが10倍の場合、割安と判断されることがあります。ただし、業績や将来性を加味することが重要です。
例2:成長企業への投資
PERが高くても、EPS成長率が大きい企業では株価上昇の余地があります。将来利益が増加する見込みがあるかを確認します。
| 銘柄 | 株価 | EPS | PER | 投資判断 |
|---|---|---|---|---|
| 銘柄A | 1,000円 | 100円 | 10倍 | 割安だが成長性を要確認 |
| 銘柄B | 1,500円 | 100円 | 15倍 | 業種平均並み |
| 銘柄C | 2,000円 | 100円 | 20倍 | 割高だが成長株の可能性あり |
第5章:PERを活用した投資戦略
- バリュー投資:PERが低く割安な銘柄を選び、将来の株価上昇を狙う
- グロース投資:EPS成長率の高い銘柄で高PERでも投資価値を見込む
- 業種比較分析:同業種内のPER比較で割安銘柄を特定する
- PERとROEの組み合わせ:PERだけでなく、ROEや利益成長率も確認して総合判断
第6章:PER活用時の注意点とリスク
- PERは過去や予想のEPSに依存するため、業績予想が外れると誤判断の原因になる
- 一時的な利益変動や赤字企業ではPERが高騰または計算不能になることがある
- 単独での判断は危険。必ず業績・成長率・業界比較などとセットで評価する
第7章:応用例とケーススタディ
ケース1:成熟業種の割安株発掘
EPSが安定している製造業でPERが業種平均より低い場合、割安株として購入を検討できます。
ケース2:急成長銘柄の評価
ITやバイオなど成長業種でPERが高くても、EPS成長率が20%以上見込める場合、投資対象として魅力的です。
第8章:まとめ
PERは株価と利益の関係を示す代表的な指標です。適切に活用すれば、割安株の発掘や成長株への投資判断に役立ちます。 ただし、単独での判断はリスクが高いため、EPSの成長性やROE、業界平均などと組み合わせることが重要です。
- 過去PERと予想PERを理解して使い分ける
- 業種平均との比較で相対的割安・割高を判断する
- PERだけに頼らず、ROEや利益成長率とセットで総合判断する
- 成長株の場合、高PERでも投資価値がある場合がある
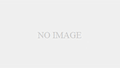

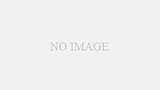
コメント